基準価額の推移
運用実績
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヵ月 | △0.76% |
| 3ヵ月 | △1.54% |
| 6ヵ月 | 0.44% |
| 1年 | 0.04% |
| 3年 | △0.89% |
| 設定来 | 32.55% |
| 決算期 | 分配金 |
|---|---|
| 2020年9月 | 0円 |
| 2021年9月 | 0円 |
| 2022年9月 | 0円 |
| 2023年9月 | 0円 |
| 2024年9月 | 0円 |
| 設定来合計 | 0円 |
参考指標
| ファンド | 国内株式 | 国内債券 | |
| 年率リターン | +3.1% | +9.7% | -0.4% |
| 標準偏差 | 7.3% | 18.6% | 2.4% |
| 下方偏差 | 8.2% | 19.4% | 2.4% |
| シャープレシオ | 0.42 | 0.52 | -0.17 |
| ソルティノレシオ | 0.38 | 0.50 | -0.17 |
| 最大ドローダウン | -19.3% | -32.2% | -12.3% |
| 相関 | - | 0.54 | 0.00 |
資産配分(作成基準日時点)

| 資産クラス | 基本資産 配分比率 |
作成基準日 時点比率 |
| 日本株 | 13.00% | 12.73% |
| 先進国株(米国) | 13.00% | 12.39% |
| 先進国株(除く米国) | 5.00% | 4.91% |
| 新興国株 | 2.00% | 1.96% |
| 先進国債券(米国) | 0.00% | 0.00% |
| 海外債券(グローバル除く米ドル建て) | 0.00% | 0.00% |
| 国内リート(日本) | 5.50% | 5.57% |
| 海外リート(米国) | 4.00% | 4.04% |
| ヘッジファンド(GCIシステマティック・マクロファンドVol10 クラスA) | 54.50% | 39.60% |
| ヘッジファンド(GCIディバーシファイドアルファファンド クラスA) | 14.02% | |
| 現金、その他 | 3.00% | 4.80% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |
各資産の寄与額(概算)
ファンドマネージャーのコメント
<運用の基本スタンス>
「GCIエンダウメントファンド(以下当ファンドといいます)」は、さまざまな市場環境を乗り越えて、長期間にわたるすばらしい運用実績を残してきたエンダウメント(大学財団)型の投資戦略をお手本に、オルタナティブ投資を積極的に活用したグローバル分散投資を行います。リスクとリターンの源泉を分散・多様化するとともに、運用コストにも注意を払い、運用資産の長期的成長を効率的に目指します。
当ファンドの運用手法はシンプルかつ頑健(Robust)です。原則として年一回、基本資産配分(ターゲット・ポートフォリオ)を決定した上で、適宜リバランスを実行し、資産配分を維持します。
基本資産配分(ターゲット・ポートフォリオ)は、想定リスクを年率8%にセットし、対象資産の流動性やキャパシティ(市場規模)などを吟味して選択した投資対象ユニバースの中で、最良の期待リターンとなるように配分比率を決定します。その時々の市場動向やムードなどに過度に振り回されず、取引コストを抑制しながら、一定のリスクを効率的に取り続けるという、ブレのない運用姿勢を貫きます。
長期資産形成において、もっとも重要なのは「継続」です。ときによって、うまくいくことも、そうでないときもありますが、途中で止めてしまう(その多くは損切りしてしまう)ことを避けるべく、「分散」効果を活用したリスク管理を重視します。
<ビッグ・ピクチャー>
2024年9月、当ファンドは年に一度の基本資産配分の点検に合わせて、その前提となるビッグ・ピクチャー(10年程度の時間軸でマクロ環境を俯瞰した投資環境の認識)の定期的な点検を行いましたが、以下の通り、特段の変更はありません。
当ファンドが運用を開始したのは2015年9月ですが、そこからさらに15年遡る2000年4月の当社設立以来、①グローバル化、②経済の市場化、③情報通信革命(IT化)という20世紀末に生じた3つの大きなトレンドが、経済成長の力強いエンジンになると同時に、ディスインフレ圧力となって低インフレ・低金利時代が長期化するというビッグ・ピクチャーを堅持してきました。そして、コロナ禍と地政学リスクの顕在化がきっかけとなり、1980年代以降長く続いてきた世界的なディスインフレと金利低下トレンドには終止符が打たれました。
数十年単位の長期スパンでみると、第二次世界大戦時の戦費調達のため米国などで実施された財政ファイナンス(大量の国債を中央銀行が買い入れる措置)とその後の石油危機により、1940年から1980年まで40年間のインフレの時代がありました。その後、1980年以降40年間はグローバル化を背景にしたディスインフレ時代が続きましたが、それを政策的に後押ししたリーマン危機後の未曾有の量的金融緩和と財政拡張が、コロナ禍と地政学リスクの顕在化(ロシアによるウクライナ侵攻と米中対立)を契機に大きな転機を迎えたものと考えています。
グローバル化は、平和の配当を通じて経済成長という恩恵をもたらした一方、格差拡大や内向き志向などの副作用も顕在化しました。しかしながら、人類の自由への希求と技術革新が停滞するとは考えにくく、グローバル化という太く大きな潮流自体は不変だと考えます。デジタル化(DX)や脱炭素などを強力なドライバーとして、紆余曲折を経ながらもグローバル経済は成長を続けていくことが期待されます。一方、低インフレを背景に主要国が続けてきた緩和的な財政金融政策がとうとう行き着くところまで行き、反転したことはおそらく間違いなく、ディスインフレが終わってインフレ的な環境に移行したものと思われます。
資産運用という観点では、主要国の歴史的金融緩和政策を受けて債券高・株高が続いたことから、シンプルなパッシブ運用が良好なパフォーマンスを上げました。為替市場でドル高円安が大きく進んだことから、日本の円建て投資家にとっては為替をオープンにすることで、ヘッジコストを避けるだけでなく、為替差益を享受することも可能でした。結果的に、円建ての期待リスクを最優先に管理し、そのうえでリターンの極大化を目指していく当ファンドにとっては相対的に逆風の環境でした。しかしながら、今後は一市場ボラティリティが高まり、運用環境も変化するのではないかと考えています。
そのような不確実性の高い環境では、「分散」とそれに基づくリスク管理が最善の対応のひとつと考えています。米国大学エンダウメント型のポートフォリオをお手本とする当ファンドの特徴はオルタナティブの活用です。とくに、ショート・ポジション(売りから入る)をとることも可能なヘッジファンドを利用することで、効果的な分散効果と安定したリターンを得ることができると考えています。
当ファンドは、市場環境にかかわらず、円建ての変動リスクを想定の範囲内に抑制することに努め、資産価値の保全を最優先しながら、人類とグローバル経済の成長をリターンの源泉として、長期的な成長を目指してまいります。受益者のみなさまにおかれましても、こうした投資哲学・運用に対するブレない姿勢をご理解いただき、腰を据えた長期資産運用・資産形成にご一緒にお取り組みくださいますよう、お願い申し上げます。
<基本資産配分>
ビッグ・ピクチャーを前提として、2024年9月に年1回の基本資産配分の点検を行いました。
最優先目標であるファンドのリスクですが、年率7.3%(目標 年率8%)と想定通りです。
一方、今回の焦点は①債券の配分比率、②為替ヘッジでしたが、結論としてはいずれも現状維持とし、ヘッジファンド内の配分比率の微調整を実施するにとどめました。
- 金利上昇(債券価格下落)や為替ヘッジコストの上昇などから、配分を落としてきた債券(国内・海外)ですが、欧米で利下げが実施され、株式との逆相関構造回復の兆候もみられます。しかしながら、日米の金融政策や、政治関連の重要イベントを控え、インフレや財政懸念の再燃による金利上昇リスクも軽視できないこと、為替ヘッジ後の利回りは依然としてマイナスとなることから、変更を見送ります。ただし、今後の米国大統領選挙などの市場イベント次第では、機動的な変更も検討します。
- GCIエンダウメントファンドは円ベースでのリスク・リターンの最大化を目指す運用であり、外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行っております。日本銀行が金融政策の正常化に向けた動きを開始したことも受け、アベノミクスを背景に、75円(2011年)から160円(2024年)まで長きに及んだ歴史的円安トレンドは終焉したとみています。依然としてヘッジコストは高くつきますが、原則として為替ヘッジを継続します。
<運用経過>
2025年2月は、基本資産配分に沿ってヘッジファンドを加えたグローバルな資産に分散投資を行いました。2月の基準価額(分配金再投資)は、前月末に比べ0.76%下落しました。ファンドの基準価額に対しては、先進国株(除く米国)や新興国株、海外リート(米国)、ヘッジファンドがプラスに寄与した一方、日本株や先進国株(米国)、国内リート(日本)がマイナスに寄与しました。
<今月を振り返って>
大統領就任後、しばらくは国民の支持を受け、野党やメディアの批判も抑制気味といわれるハネムーン期間に、トランプ政権は矢継ぎ早に新政策を繰り出しています。英語でいうところの’Pro-Business’(ビジネス寄り)、そしてマーケット・フレンドリーという市場の期待に動揺が広がり、2月後半以降、株式市場とドルが急減速し、ドル長期金利も低下しました。一方、トランプ政権は、グローバルな経済秩序の再構築という「大きな仕事の前にはいろいろある」(トランプ大統領)、「経済のデトックス期間だ」(ベッセント財務長官)と意に介さず、です。
ここでは2点だけ申し上げたいと思います。
第一に、5年とか2年とか、あるいはもっと長期の株価チャートを眺めてみてください。2008年のリーマン危機以降の米国株の上昇ぶりは目を見張るものがあります。特にここ1年半近くはほぼ一本調子で最高値を更新し続けてきました。株式市場には変動がつきもので、その変動率のことをファイナンス用語ではリスクと定義するわけですが、株価は健全な調整を何度も繰り返しながら、長期的には実体経済の成長に沿って上昇していくものだという基本に戻れば、長期投資の立場からは慌てる必要はないと思います。
第二に、そうはいっても先々の不確実性が増していることは間違いなく、投資家のみなさんのそれぞれの立場で何らかのリスクを管理する上での基本原則は「分散」に尽きます。
GCIエンダウメントファンドの骨子は、リスク管理を最優先した「長期分散」投資をシステマティックに継続することです。インフレ的な環境でグローバル経済の成長から果実を期待できる株式と、市場のボラティリティを収益源のひとつとして債券に代替し得るヘッジファンドをポートフォリオの中核として、円ベースでのリスク管理を最優先し、安定的な成果を受益者のみなさまとともに目指してまいります。
ファウンダー・代表取締役CEO兼社長 山内英貴
※上記コメントは、2025年3月11日に作成したものです。
投資対象ファンド(投資信託証券)-上場投資信託(ETF)の基準価額推移
投資対象ファンド(投資信託証券)-GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスAの状況
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヵ月 | +0.93% |
| 3ヵ月 | -2.17% |
| 6ヵ月 | +0.92% |
| 1年 | -4.05% |
| 3年 | +9.00% |
| 組入来 | +5.47% |
※上記グラフは、当ファンドの組入対象である「GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスA」の当ファンド計上日ベースの基準価額を、当ファンドへの組入開始日(2018年6月8日)を10,000として指数化し、作成基準日までを表示したものです。
※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
※ 上記ポートフォリオ断面のグラフは、ポジションを構築するにあたって差し入れる証拠金の対純資産総額比率です。マイナスはショートポジションを意味します。証拠金はリスク見合いで差し入れるものであるため、当該指標はポートフォリオにおけるリスクをより実態に近い形で表すものと考えられています。
※ 上記損益内訳は信託報酬、成功報酬等控除前のものです。
投資対象ファンド(投資信託証券)-GCIディバーシファイドアルファファンド クラスAの状況
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヵ月 | -1.26% |
| 3ヵ月 | -2.74% |
| 6ヵ月 | -0.73% |
| 1年 | -4.22% |
| 3年 | -20.96% |
| 組入来 | -27.03% |
※上記グラフは、当ファンドの組入対象である「GCIディバーシファイドアルファファンド クラスA」の当ファンド計上日ベースの基準価額を、当ファンドへの組入開始日(2021年7月19日)を10,000として指数化し、作成基準日までを表示したものです。
※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
※ 上記ポートフォリオ断面のグラフは、ポジションを構築するにあたって差し入れる証拠金の対純資産総額比率です。マイナスはショートポジションを意味します。証拠金はリスク見合いで差し入れるものであるため、当該指標はポートフォリオにおけるリスクをより実態に近い形で表すものと考えられています。
※ 上記損益内訳は信託報酬、成功報酬等控除前のものです。
投資対象ファンド(投資信託証券)-GCIマネープールマザーファンドの状況
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヵ月 | +0.03% |
| 3ヵ月 | +0.03% |
| 6ヵ月 | +0.04% |
| 1年 | +0.06% |
| 3年 | -0.03% |
| 組入来 | -0.23% |
当資料で使用した指数について
※当資料に使用している指数については以下の通りです。
国内株式:TOPIX(配当込み)
国内債券:Bloomberg Asian Pacific Japanese Yen TR Index Value Unhedged JPY
< 当資料で使用したブルームバーグ・インデックスについて >
出典:「Bloomberg®」およびブルームバーグ債券インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、株式会社GCIアセット・マネジメントによる特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは株式会社GCIアセット・マネジメントとは提携しておらず、また、GCIエンダウメントファンド(成長型)を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、GCIエンダウメントファンド(成長型)に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
※使用している各指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
「GCIエンダウメントファンド」特設サイトのご案内
GCIエンダウメントファンドの特設ページを開設しました。
ファンドの特色や運用状況、過去の月次レポート等を掲載しています。
今後、新着情報や臨時レポートなども掲載していく予定です。
是非、ご覧ください。
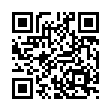
https://endowment.jp/
※パソコン・スマートフォン共通

組入資産の市場動向コメント
<株式>
2025年2月のグローバル株式市場は地域毎にまちまちの動きとなりました。米国では、米長期金利の低下や堅調な企業業績を背景に月半ばにかけて株価は堅調に推移し、S&P500指数は史上最高値を更新しました。しかし、月後半にかけては、弱めの経済指標が相次ぎ米国経済の景気減速が意識されたほか、トランプ大統領が関税を強化する姿勢を示したことなどから先行きへの警戒が高まり、株価は大きく下落する展開となりました。欧州では、トランプ政権による関税政策への不透明感が重石となりましたが、欧州中央銀行(ECB)による追加利下げ期待やウクライナ戦争の停戦期待を支えに株価は上昇し、欧州の主要株価指数は史上最高値を更新しました。日本では、為替の円高進行が重石となったほか、トランプ政権による関税政策への警戒などから自動車や半導体関連株を中心に株価は大きく下落し、日経平均株価は38,000円を割り込みました。
<債券>
2025年2月のグローバル債券市場は地域毎にまちまちの動きとなりました。各国国債利回りは、米欧金利が低下した一方、日本金利は上昇しました。米国では、インフレの再加速が警戒され金利は上昇する場面も見られましたが、小売売上高など複数の経済指標が弱めの結果を示したことで米国経済の景気減速懸念が強まり、金利は低下しました。米連邦準備制度理事会(FRB)が保有資産圧縮の一時停止や減速を議論したことが明らかとなったことも米国債の需給改善を連想させ、月末にかけて金利は低下基調が継続しました。欧州では、ウクライナ戦争の停戦期待を背景に、今後の防衛費増加による国債増発が意識され金利は上昇する場面も見られましたが、米長期金利の低下やECBによる追加利下げ期待を支えに、金利は低下しました。日本では、消費者物価指数が高い伸びを示したことなどから、引き続き日銀の追加利上げ観測は強く、金利は上昇しました。日本10年国債利回りは一時1.455%と約15年ぶりの高水準をつける場面もありました。クレジット市場におけるクレジット・スプレッド(企業等の信用力を示す、国債に対する上乗せ利回り)は、トランプ政権による関税政策の不透明感が重石となりハイイールド債が小幅に拡大し、その他は概ね横ばいとなりました。
<不動産投資信託(REIT)>
2025年2月のREIT市場は地域毎にまちまちの動きとなりました。米国REITは、米国景気の減速懸念や米株式相場の下落が重石となったものの、米長期金利の低下を好感し上昇しました。国内REITは、国内長期金利が約15年ぶりの高水準に上昇したことが重石となり、軟調に推移しました。東証REIT指数の用途別では、オフィス向けがアウトパフォームした一方、住宅向けがアンダーパフォームし、商業・物流向けはほぼ指数並みのパフォーマンスとなりました。
<ヘッジファンド市場全般>
2025年2月のヘッジファンド市場は総じて下落しました。戦略別では、債券アービトラージ戦略やイベントドリブン戦略、株式マーケット・ニュートラル戦略などが上昇しアウトパフォームした一方、CTA戦略やトレンドフォロー戦略などが下落しアンダーパフォームするなど、まちまちとなりました。
投資リスク
基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
基準価額の変動要因となる主なリスク
- 株価変動リスク
- 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢などにより変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
- 金利変動リスク
- 債券などの価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。なお、債券などが変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者などの財務状況の変化などおよびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢などにより変動します。債券などの価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
- リートの価格変動リスク
- リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格など)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制などの変更、災害などの要因により変動します。また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化などにより価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
- 為替変動リスク
- 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢などの様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、当ファンドおよび投資対象ファンド(投資信託証券)において、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
- 信用リスク
- 有価証券等の発行体などが財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金などをあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
- カントリーリスク
- 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化などにより市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、方針に沿った運用が困難となり、基準価額が下落することがあります。特に、新興国への投資には、先進国と比較して政治・経済および社会情勢の変化が組入銘柄の価格に及ぼす影響が相対的に高い可能性があります。
- 流動性リスク
- 時価総額が小さい、取引量が少ないなど流動性が低い市場、あるいは取引規制などの理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
- ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
- 投資対象ファンド(投資信託証券)においては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引などの買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、当ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンド(投資信託証券)の純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンド(投資信託証券)の基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。 また、ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
お申込みメモ
購入時
- 購入単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入価額
購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
(ファンドの基準価額は1万口あたりで表示しています。)
- 購入代金
販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金時
- 換金単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金価額
換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額とします。
- 換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
購入・換金に関して
- 申込締切時間
原則として、購入・換金のお申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日のお申込み受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入・換金の申込受付不可日
ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日
※詳しい申込受付不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
- 換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
- 購入・換金申込受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害など)が発生したときなどには、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みを取り消すことがあります。
その他
- 信託期間
原則として無期限(2015年9月25日設定)
- 繰上償還
次のいずれかの場合などには、繰上償還することがあります。
- ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき
- 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
- やむを得ない事情が発生したとき
- 決算日
毎年9月25日(休業日の場合は翌営業日)
- 収益分配
年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託金の限度額
10兆円
- 公告
原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。
URL:https://www.gci.jp
- 運用報告書
毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
- スイッチング
販売会社によっては、安定型との間でスイッチング(乗換え)が可能です。
※スイッチングの際には換金時と同様に換金されるファンドに対して税金などをご負担いただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 課税関係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「少額投資非課税制度(NISA)」の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※上記は2024年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
- 購入時手数料
購入価額に1.1%(税抜1.0%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入時手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務などの対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
- 信託財産留保額
換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
- 運用管理費用 (信託報酬)
純資産総額に対し年率0.5258%(税抜 0.478%)以内
運用管理費用(信託報酬)は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。信託報酬率およびその配分は、ファンドの純資産総額の残高に応じて変更します。<信託報酬率およびその配分>
純資産総額
信託報酬率
<合計>支払先の配分 委託会社 販売会社 受託会社 500億円以下部分 年率0.5258%
(税抜 0.478%)年率0.1408%
(税抜 0.128%)年率0.33%
(税抜 0.3%)年率0.055%
(税抜 0.05%)500億円超
1,000億円以下部分年率0.4488%
(税抜 0.408%)年率0.1078%
(税抜 0.098%)年率0.297%
(税抜 0.27%)年率0.044%
(税抜 0.04%)1,000億円超部分 年率0.3718%
(税抜 0.338%)年率0.0748%
(税抜 0.068%)年率0.264%
(税抜 0.24%)年率0.033%
(税抜 0.03%)役務の内容 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用、基準価額の算出、開示資料の作成などの対価 購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続きなどの対価 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行などの対価 〈投資対象ファンド(投資信託証券)における運用報酬等〉
年率0.6897%程度(税抜 0.6877%程度)+成功報酬
※当ファンドにおいては成功報酬はかかりませんが、指定投資信託証券(GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスAおよびGCIディバーシファイドアルファファンド クラスA)においては20%の成功報酬がかかる場合があります。
*指定投資信託証券(GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスAおよびGCIディバーシファイドアルファファンド クラスA)の基準価額(管理報酬等控除後、成功報酬控除前)がハイ・ウォーター・マークを超えた場合には、その超過分に対して20%の成功報酬がかかります。当該報酬は計算期間(GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスA:6月1日から翌年5月31日まで、GCIディバーシファイドアルファファンド クラスA:4月1日から翌年3月31日まで)を通じて日々計上(ハイ・ウォーター・マークを下回った場合は戻し入れ)され、原則、計算期間終了後に年1回支払われます。ハイ・ウォーター・マークとは、前計算期間までで最後に成功報酬が控除された際の基準価額(成功報酬控除後)をいい、計算期間終了時に更新されます。〈実質的な負担〉
年率1.2155%程度(税抜 1.1657%程度)+成功報酬
※ 当ファンドの運用管理費用(信託報酬)に投資対象ファンド(投資信託証券)の運用報酬等を合わせた、投資者が実質的に負担する額の合計です。
※ 投資対象ファンド(投資信託証券)における運用報酬等ならびに実質的な負担の値はあくまで目安であり、指定投資信託証券の実際の組入れ状況等により変動する場合があります。
※ 指定投資信託証券(GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスAおよびGCIディバーシファイドアルファファンド クラスA)において20%の成功報酬がかかる場合、上記実質的な負担も相応分上がります。
※ 上記は2024年9月末現在のものです。
その他の費用・手数料
- <売買委託手数料など>
有価証券売買時の売買委託手数料、立替金の利息、ファンドに関する租税などが信託財産から支払われます。これらの費用は運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
- <信託事務の諸費用>
監査費用、印刷費用、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用などの諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1%を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
関係法人
- 委託会社
- 株式会社GCIアセット・マネジメント
[ファンドの運用の指図を行う者] -
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第436号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会
-
照会先 電話番号 03(6665)6952 (営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.gci.jp
- 受託会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
[ファンドの財産の保管及び管理を行う者]
販売会社一覧
ご留意事項
- 当資料は、株式会社GCIアセット・マネジメント(以下「当社」といいます)が、当ファンドの投資判断の参考となる情報提供を目的として作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 当ファンドのお申込みにあたっては必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
- 当資料記載のデータや見通し等は、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報をもとに作成しておりますが、正確性、適時性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は、作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、参考として記載されたものであり、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
- 各指数に関する著作権等の知的財産、その他一切の権利は、各々の開発元または公表元に帰属します。
- 当資料に関する一切の権利は、引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製はできません。
- 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、銀行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
